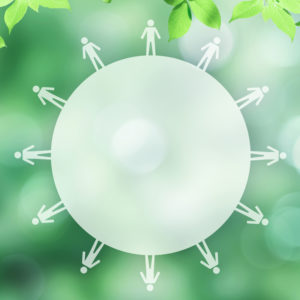「多様性(ダイバーシティ)」という言葉は、今や社会のあらゆる場面で使われるキーワードとなりました。企業の採用ページ、行政の政策文書、学校教育の現場、メディアの報道——いずれにも「多様性を尊重すること」が推奨され、実現すべき理想とされています。けれども、この「多様性」とは、果たして誰のために、何のために、必要とされてきたのでしょうか。
多くの人は、「多様性」と聞くと、真っ先にLGBTや障がい者、あるいは外国人労働者など、社会的に少数派とされる人々の権利や尊厳をめぐる議論を思い浮かべるかもしれません。実際、「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」の取り組みは、こうしたマイノリティへの理解と配慮から始まったと言っても過言ではありません。
しかし、そもそも「多様性」とは、単にマイノリティの人権を擁護することだけにとどまるものではありません。むしろその本質は、「違いのある他者と、どう共に生きるか」という、私たち全員に関わる問いなのです。
たとえば、年齢の違いもまた「多様性」の一つです。若者には新しい感性と行動力があり、中年世代には実務の経験と責任感があり、老年世代には人生の蓄積と長期的な視点があります。ところが、しばしば職場では「年配者は頭が固い」「若者は何も知らない」といった固定観念が支配し、それぞれの世代が互いの価値を見失いがちです。
けれども、年齢による多様性こそが、組織に奥行きと柔軟性をもたらします。たとえば、ある若手社員がSNSやAIを活用した新しい施策を提案し、ベテラン社員がそれを現場の文脈に合わせて実行可能な形に整える——そんな協働があってこそ、革新と安定が両立します。つまり、「違い」は対立ではなく、補完の関係になりうるのです。
また、多様性が重視される背景には、歴史的な教訓があります。20世紀、世界は何度も「同質性」を過剰に求める体制のもとで、大きな悲劇を経験しました。ナチス・ドイツによる人種差別や、日本における戦時中の異論排除、アメリカの黒人差別といった事例を思い出せば明らかなように、「異なる存在を排除すること」は、やがて社会全体の不自由と閉塞を招きます。
だからこそ21世紀の社会は、あえて「違い」に目を向け、それを受け入れることを選び始めました。多様性は、人権の尊重という理念に根ざしつつも、より実利的な文脈——たとえば「創造性の向上」「組織のレジリエンス(回復力)」「グローバルな競争力」といった観点からも推奨されています。
しかし、ここで重要なのは、多様性の尊重が「特定の誰かのため」ではなく、「社会全体の健やかさのため」に行われるという点です。違うからこそ新しい視点が生まれ、違うからこそ摩擦を通じて成長がある。そう考えると、多様性とは、単なる「寛容」の問題ではなく、むしろ「社会の成熟度」を測る指標であると言うことができます。
日本では、ともすれば「空気を読む」とか「和をもって貴しとなす」といった文化が、多様性を「面倒なもの」と捉えてしまう傾向があります。しかし本来の「和」とは、違いを消すことではなく、違いを前提とした調和を目指すことではなかったでしょうか。
今、多くの組織が「イノベーション」や「持続可能性」を模索する中で、本当に求められているのは、「多様な声に耳を傾ける力」であり、「異なる価値観をつなぎ合わせる知恵」です。その土壌を育てることこそが、真の意味での「多様性の推進」ではないかと思うのです。
性別、国籍、年齢、宗教、価値観——どんな「違い」も、まずは一つの可能性として尊重されること。その上で、どう共に働き、学び、生きていくかを模索すること。それが、多様性を讃える社会の、本当の出発点なのではないでしょうか。世界のあちこちで社会の「分断」の動きが広がっている今だからこそ、「多様性」の本来の意味について、もう一度原点に戻って考える必要があります。